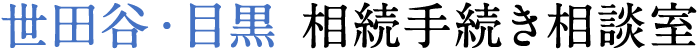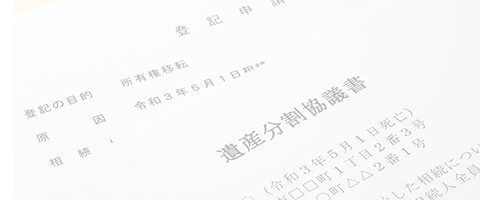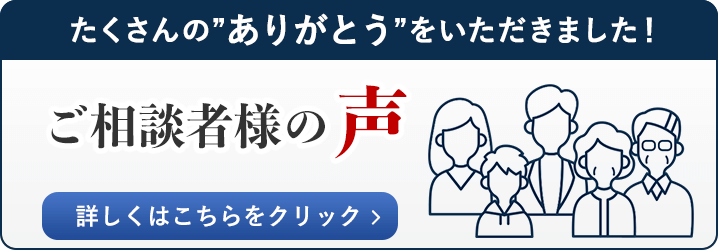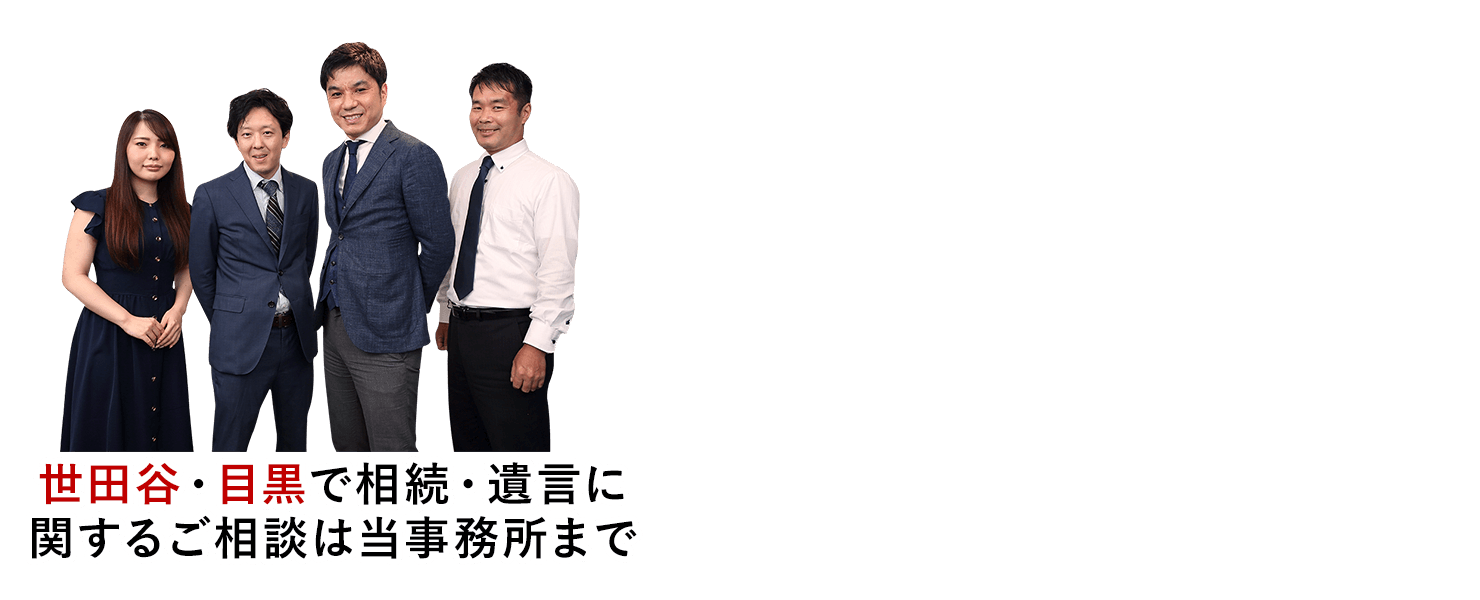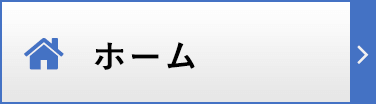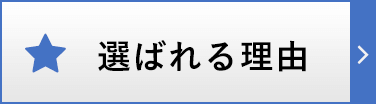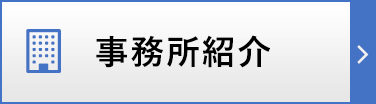遺留分の請求方法|2019年改正遺留分侵害額請求権について解説
遺言で財産を貰えなかった場合はどうすればいい?
亡くなった方が遺言を遺していた場合、基本的にその内容に従って遺産は分配されることになります。
遺言では法定相続分とは異なる割合で財産の配分を指定することも可能ですし、相続人以外の方に財産を渡すことも可能です。

遺留分をもらうには?
特定の相続人の方に一切遺産を相続させないとすることも可能です。
しかし、それでは遺産を貰えない相続人にとってあまりに不公平という事で、法定相続人には「遺留分」として一定額の金銭の支払いを求める権利が認められています。
本記事では、2019年の民法改正に伴う変更点を踏まえ、遺留分の請求方法と注意点についてくわしく解説します。
相続手続き・生前対策に関する無料相談実施中!
相続に向けて生前にできる対策や、相続が発生した場合にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、円満相続を実現するための生前対策や、身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では遺留分の請求に関する業務は取り扱っておりません。従ってすでに発生した相続について遺留分に関するご質問をいただきましても一切お答えすることはできません。遺留分侵害額請求を検討している方や請求を受けた方は弁護士にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069
遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている相続財産を取得できる権利のことをいいます。
遺言を遺せば、特定の相続人に多くの財産を相続させたり、相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことも可能です。
しかし、その結果財産を少ししか(あるいはまったく)貰えない相続人がいる場合、その方は財産を多く貰った相続人等に対して遺留分相当の金銭の支払いを請求することができます。
この金銭の支払いを請求できる権利のことを、「遺留分侵害額請求権」と言います。
遺留分の請求ができる相続人
遺留分は法定相続人であれば誰でも認められるわけではなく、請求できるのは以下の相続人に限られます。
【遺留分の請求ができる相続人】
・配偶者
・子(代襲相続人である孫含む)
・直系尊属(父母や祖父母)
兄弟姉妹(及び代襲相続人である甥姪)はたとえ法定相続人であっても遺留分の請求をすることはできません。
各相続人の遺留分の割合

遺留分は各相続人ごとに請求できる割合が決まっています。
相続人ごとの遺留分の割合は、相続のケースによっても異なりますが、大まかに言うと、本来の法定相続分の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人のケース(亡くなった方に配偶者や子がおらず、父母が存命のケースなど)では本来の法定相続分の3分の1になります。
くわしくは下表のとおりとなります。
■相続のケースごとの遺留分割合
| 相続人 | 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | 直系尊属の遺留分 | 兄弟姉妹の遺留分 | 遺留分の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | - | - | 無 | 1/2 |
| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4 | - | 無 | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | - | 1/6 | 無 | 1/2 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | - | - | 無 | 1/2 |
| 子のみ | - | 1/2 | - | 無 | 1/2 |
| 父母のみ | - | - | 1/3 | 無 | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | - | - | - | 無 | 無 |
※代襲相続人である孫は「子」に含みます。
※父母が二人いたり、子供が複数人いる場合は、それぞれの遺留分を頭割りします。
※代襲相続人の遺留分は被代襲者(先に死亡した親)の遺留分を頭割りした割合になります。
遺留分の具体的な計算方法など、遺留分制度の概要についてくわしくはこちらの記事をご参照下さい。

遺留分を請求できる期間

遺留分の請求は相続人に認められた権利ですが、いつまでも請求できるとすると、相続人・受遺者だけではなく第三者にも迷惑がかかるので請求できる期間が決められています。
以下の2つの期間のいずれかを経過すると、遺留分を請求できる権利は消滅してしまいます。
1.相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
2.相続開始の時から10年
上記のうち、1(「消滅時効」と言います。)については相続の開始を知っていたとしても、遺言書や贈与の存在を知らない限りは、時効は進行しません。
また、期間内に相手方に対して遺留分を請求する旨の意思表示をすれば消滅時効を止めることができます。
意思表示の方法に決まりはありませんが、期間内に通知をしたという確実な証拠を残すために、通常は内容証明郵便によって行います。
一方、2(「除斥期間」と言います。)については本人が相続開始の事実や遺贈や贈与がある事を知っていたかどうかに関わらず、相続開始から10年の経過によって請求できなくなってしまいます。
また、消滅時効のように遺留分請求の意思表示によって権利消滅を止めることはできません。
円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺留分の対象となる財産

遺留分請求の対象となるのは、相続開始時点の被相続人の財産及び被相続人が贈与した財産です。
遺産及び贈与した財産の合計額から被相続人の債務を控除した額が、遺留分の算定の際の基礎となる財産の価額となります。
贈与について
遺留分の対象となる贈与には生前贈与と死因贈与(贈与者の死亡によって効力が発生する贈与)の2種類があります。
このうち生前贈与については、対象となる期間が定められています。
1.贈与を受けたのが相続人の場合・・・相続開始前10年以内の贈与が対象
2.贈与を受けたのが相続人以外の場合・・・相続開始前1年以内の贈与が対象
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えると知ってした贈与については、期間の制限はありません。この場合は贈与の時期が10年より前でも、また、贈与を受けたのが相続人か否かに関わらず、遺留分の対象となります。
遺留分の対象にならない財産
遺族年金や未支給年金は、法律に基づいて一定の遺族に支給される一身専属の権利なので、遺留分の対象となる財産には含まれません。
また、受取人が特定されている死亡退職金や生命保険金についても、原則として遺留分の対象となる財産には含まれません。
ただし、死亡退職金や生命保険金の金額が、遺産や生前贈与の額と比べて過大であり、相続人間に著しい不公平が生じる場合は、例外的に遺留分の対象となる可能性があります。
具体的な遺留分侵害額の計算方法

ここからは、具体的なケースに基づき、遺留分侵害額の計算方法をみてみましょう。
遺留分請求の際には、以下の金額をもとに請求額を計算します。
a.相続開始時点の被相続人の財産の総額
b.被相続人が贈与した財産の総額
c.被相続人の債務の総額
d.自分の遺留分割合(参照)
e.上記aのうち遺留分権利者が相続した財産の価額
f.上記bのうち遺留分権利者が贈与を受けた財産の価額
g.上記cのうち遺留分権利者が負担する債務の額
上記それぞれの金額をもとに、以下の計算式によって遺留分侵害額を計算します。
【遺留侵害額の計算式】
1.{(a+b)-c}×d=自分の遺留分
2.上記1で求めた自分の遺留分-(e+f)+g=遺留分侵害額
上記2で求めた金額を、遺留分侵害額として財産を多く貰った方に対して請求できます。
なお、上記2の計算結果がマイナスの場合は、遺留分より多くの財産を貰っていることになるので、遺留分を請求することはできません。(場合によっては他の方に遺留分侵害額を支払わなければならない可能性があります。)
■具体例に基づく計算
・被相続人は父A、相続人は子B及びCの二人。
・相続開始時点の財産総額は5,000万円。
・Bに対して4,000万円、Cに対して1,000万円を相続させるとのAの遺言がある。
・贈与の額はBに600万円、Cに200万円。(いずれも相続開始前10年以内の贈与)
・相続債務は総額200万円でBが150万円、Cが50万円を負担する。
【Cの遺留分侵害額の計算】
1.{(5,000万円+800万円)-200万円}×1/4=1,400万円(Cの遺留分)
2.1,400万円-(1,000万円+200万円)+50万円=250万円(Cの遺留分侵害額)
上記の事例ではCはBに対して250万円を遺留分侵害額として請求することができます。
遺留分侵害者が複数いる場合の負担の順序

遺留分を侵害する財産を貰った方が複数いる場合は、それぞれが負担する金額は以下の順序によって決まります。(民法第1047条第1項)
【遺留分負担の順序】
① 相続(遺贈)で遺産を貰った人と贈与で財産を貰った人がいる場合
→相続(遺贈)で遺産を貰った人が先に負担する。
② 相続(遺贈)で遺産を貰った人が複数いる場合
→貰った遺産の価額の割合に応じて負担する。(ただし遺言で指定がある場合は、その指定された割合に従う。)
③ 贈与で財産を貰った人が複数いる場合
→財産を貰った時期が新しい人から先に負担する。同時に貰った場合は財産の価額の割合に応じて負担する。
上記の順序に従って、各人が相続及び贈与で貰った額を上限として遺留分侵害額を負担します。
ただし、負担するのが相続人である場合は、相続及び贈与で貰った額からその人の遺留分額を控除した金額が上限となります。遺留分の請求を受けても自分の遺留分は保証されるということです。
■具体例に基づく計算
【事例①】
・被相続人は父A、相続人は子B、C及びDの3人。
・相続開始時点の財産総額は5,000万円。
・Bに対して3,000万円、Cに対して1,500万円、Dに対して500万円を相続させるとのAの遺言がある。(遺留分の負担について別段の指定は無し。)
・生前贈与及び死因贈与は無し。
・相続債務は総額200万円でBが全額を負担する。
【Dの遺留分侵害額の計算】
1.{(5,000万円+0万円)-200万円}×1/6=800万円(Dの遺留分)
2.800万円-(500万円+0円)+0円=300万円(Dの遺留分侵害額)
【遺留分侵害額の負担の計算】
1.BとDはどちらも相続により遺産を貰っているので、貰った遺産の割合に応じて按分負担する。
2.Bの貰った遺産3,000万円、Cの貰った遺産1,500万円なので、負担割合はBが2/3、Cが1/3。
3.Dの遺留分侵害額300万円に負担割合をかけると、Bが200万円、Cが100万円。
4.DはBに対して200万円、Dに対して100万円を請求できる。
【事例②】
・被相続人は父A、相続人は子B及びCの二人。
・相続開始時点の財産総額は1,500万円。
・Bに対して1,200万円、Cに対して300万円を相続させるとのAの遺言がある。(遺留分の負担について別段の指定は無し。)
・生前贈与の額は相続開始の5年前にBに500万円、半年前に内縁の妻Eに対して2500万円、Cに対しては無し。
・相続債務は総額200万円でBが全額を負担する。
【Cの遺留分侵害額の計算】
1.{(1,500万円+3,000万円)-200万円}×1/4=1,075万円(Cの遺留分)
2.1,075万円-(300万円+0円)+0円=775万円(Cの遺留分侵害額)
【遺留分侵害額の負担の計算】
1.受贈者より受遺者が優先して負担するので、まずBが負担する。
2.Bは相続で貰った財産から負担上限額125万円(1,200万円-Cの遺留分額1075万円)を負担する。
3.残り650万円については、生前贈与の時期が新しいEが全額を負担する。
4.CはBに対して125万円、Eに対して650万円を請求できる。
誰に遺留分を請求するかは、遺留分権利者の任意なので、例えば上記事例②で、内縁の妻Eに対してのみ遺留分を請求して、きょうだいであるBには請求しないことも可能です。
ただし、その場合でもEに対して請求できるのは650万円までで、Bの負担分125万円をEに請求することはできません。
また、上記事例②でEがすでに生前贈与された財産全額を使い切ってしまっていて、支払い能力が無い場合でも、その分多めにBに請求することはできません。(民法第1047条第4項)
参考(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
(中略)
四 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

2019年民法改正による変更点

遺留分を請求する権利は、以前「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年7月1日に施行された改正民法により「遺留分侵害請求権」と呼称が変わりました。
以前の「遺留分減殺請求権」は、遺留分請求の意思表示によって、各相続財産の現物について、法律上当然に遺留分相当の共有持分を取得するという制度でした。
しかし相続財産が不動産の場合、共有状態解消をめぐって問題が長期化しやすいというデメリットがありました。
そこで改正後の制度では現物を取得するのではなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利に変わりました。
これによって相続財産が不動産でも共有問題を生じることなく、早期に解決しやすくなりました。
また、民法改正によって遺留分の対象となる生前贈与の期間も変更になっています。
改正以前は、相続人への贈与は10年以内という制限はなく、どこまでも遡って対象となることが基本でしたが、何十年前の贈与を持ち出されても、かえって公平性を欠く結果になるケースもあるという事で、改正後は悪質なケースを除いて、最長10年間に限定されることになりました。
なお、改正民法が適用されるのは、2019年7月1日以降に発生した相続であり、それより前に発生した相続については改正前の規定が適用となるので注意してください。
遺留分の請求方法・手続きの流れ

遺留分を請求するためには、遺留分を侵害された相続人が自ら権利を行使する必要があります。
遺留分侵害額請求の方法について、決まった手順はありませんが、一般的には以下のような流れで進むことが多いです。
※クリックすると各手順についての詳しい解説に移動します。
↓
↓
↓
以下、それぞれの手順についてくわしく解説します。
遺留分侵害額請求の通知
遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求するためには、まず相手方(遺留分を侵害する財産を貰った方)に対して、遺留分を請求する旨の意思表示を行います。
意思表示の方法に決まりはなく、口頭での意思表示でも有効ですが、後に言った言わないで揉めないように、また、消滅時効の成立前に確実に請求したという証拠を日付入りで残すために、内容証明郵便で行うのが一般的です。
この段階では、単に遺留分を請求するという事を通知すればよく、具体的な請求金額まで特定して通知する必要はありません。
相手方との交渉

相手方に通知をしたら、具体的な遺留分侵害額について相手方と話し合いを行います。
財産が金銭のみであれば比較的計算はしやすいと思いますが、不動産がある場合は評価の方法(一般的には時価で評価することが多い)を巡って意見が分かれる可能性があるので、出来れば根拠となる資料を準備しておきましょう。
また、生前贈与について主張する場合は、昔のことになると相手方も記憶があいまいな可能性があるので、金融機関の取引履歴を取得するなどして、客観的な証拠をもとに話し合いをした方がいいでしょう。
資料収集が難しい場合や、相手方と直接やり取りをしたくない場合は、弁護士に依頼すれば代わりに調査や交渉を行ってくれます。
ここで話し合いがまとまれば、支払方法、支払いの時期を決めて、遺留分相当額を支払って終了となります。
また、後で蒸し返されないよう話し合いで決めた内容を書面にまとめ、当事者の署名と実印を押印した「遺留分侵害額に関する合意書(和解書)」などを作成しておきましょう。
遺留分侵害額調停の申立て
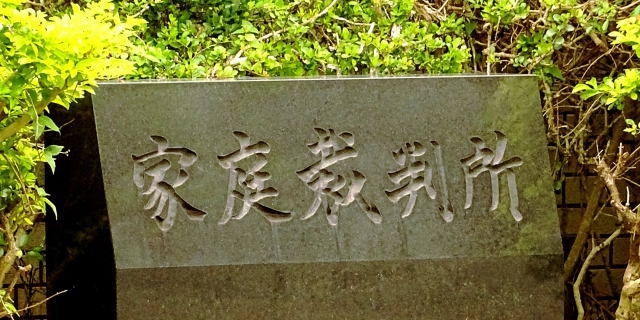
話し合いがまとまらなかった場合や、そもそも相手方から全く反応が無い場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額調停の申立てを行います。話し合いをせずにいきなり調停を申し立てることも可能です。
調停では、調停委員が当事者双方の意見を聞いて、話し合いがまとまるよう調整や提案、説得をしてくれますが、裁判ではなくあくまで話し合いのため、当事者双方が納得しなければ調停は不成立となり終了します。
調停が成立した場合は調停証書が作成されます。調停証書は判決と同様の効力を持ち、相手方が遺留分の支払いをしない場合には、強制執行(差し押さえ)をすることができます。
遺留分侵害額調停の申立ての申立先、申立てに必要な書類、手数料等は以下の通りです。
■申立てできる人
・遺留分を侵害された相続人(兄弟姉妹以外の相続人)
・遺留分を侵害された相続人の承継人(相続人,相続分譲受人)
■申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
管轄裁判所はこちらで確認できます。
■申立てにかかる費用
・申立手数料 1200円(申立書に収入印紙を貼付して納めます。)
・連絡用郵便切手 数百円~
(家庭裁判所によって異なります。詳しくは管轄裁判所にお尋ね下さい。)
■申立てに必要な書類
・申立書及びその写し(相手方の数の通数)
・遺言者の相続関係を証明するすべての戸籍謄本等
※法務局発行の「法定相続情報一覧図」を添付する場合は戸籍の提出は不要。
・遺言書の写し(又は遺言書検認調書謄本の写し)
・遺産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券に関する残高証明書、債務の額に関する資料等)
・収入印紙1200円分(申立書に貼付)
・連絡用郵便切手
※事情によってはこのほかの書類が必要になることもあります。
申立書の書式や記載例については下記裁判所ホームページにてご確認ください。
円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺留分侵害額請求訴訟の提起

調停が不成立に終わった場合、遺留分を請求したい方が遺留分侵害額請求訴訟を提起して、裁判で決着をつけることになります。(自動的に裁判に移行するわけではありません。)
なお、遺留分侵害額請求は調停前置主義が取られているため、調停をせずにいきなり裁判を提起することはできません。
訴訟の提起先は家庭裁判所ではなく、地方裁判所又は簡易裁判所になります。
管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所、相手方の住所地を管轄する裁判所、請求者の住所地を管轄する裁判所、相手方と合意した裁判所のいずれかになります。
裁判は話し合いではないため、相手方の合意は不要です。当事者の主張に基づき、裁判所が財産の評価を行い、遺留分の侵害が認められれば、遺留分相当額の金銭の支払いを命じる判決が出ます。
相手方が支払いに応じない場合は、判決に基づき強制執行することが可能です。
裁判になった場合は、遺留分侵害額について、資料を基に根拠を持って主張する必要があるので、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺留分侵害額請求と税金の関係

遺留分侵害額の請求が認められた場合、税金関係はどうなるのでしょうか?
遺留分の請求と関係してくるのは主に相続税と所得税及び住民税(譲渡所得税)です。以下、それぞれについて解説します。
遺留分侵害額請求がされた場合の相続税
被相続人の遺産の額が基礎控除額を超える場合、遺産を取得した人は相続税の申告をして相続税を納めることになります。
遺留分請求によって遺留分侵害額相当の金銭の支払いを受けた方にも、相続税の納税義務が生じます。
ただ、相続税の申告期限は、相続開始から10か月と短く、遺留分の支払額が確定した段階では期限を経過している可能性が高いので、とりあえず遺言によって指定された割合で期限内に申告(及び納税)を行うケースも多いです。
この場合、本来であれば修正申告を行い、遺留分の請求をした人はその分を納税し、請求された人が納め過ぎの状態になれば還付請求を行うことになります。
しかし、それではお互いに煩雑なため、実務上は遺留分侵害額から遺留分請求者が負担すべき相続税の金額を控除して支払うことが一般的です。
ただし、直系血族以外の方から直系血族の方に遺留分が支払われた場合など、遺留分の支払いによって相続税の総額が変わる場合(直系血族以外の方は相続税額が2割加算される)には、更正請求を行って納め過ぎた分を返金してもらう必要があります。
譲渡所得税が課税されるケースに注意!
2019年改正以降の遺留分を請求する権利は金銭債権化したため、通常は金銭の支払いによって解決となります。
この場合は相続税がかかる場合を除いて特に課税が生じることはありません。
しかし、支払いに充てるだけの金銭が用意できず、不動産や株式などの現物財産の給付によって清算した場合(代物弁済した場合)には、遺留分の請求を受けた方に譲渡所得税が課税される可能性があります。
これは、本来金銭で清算すべき遺留分を、現物で清算した場合には、その現物を売却したのと同じと考えられるためです。
現物を給付した時点でその財産に含み益(取得時と譲渡時を比べてプラスになっている場合の差額)がある場合は、利益部分(譲渡所得)に対して所得税及び住民税(譲渡所得税)が課税されてしまいます。
譲渡所得税の税率は約20~40%なので、お金が無いので現物で支払おうという方にとってはかなりの負担になるのではないでしょうか。
また、譲渡所得税の負担だけではなく、社会保険料や医療費の負担が上がる可能性もあります。家族の扶養に入っている方は扶養から外れてしまうかもしれません。
また、遺留分を請求した方にとっても、不動産を貰った場合は登録免許税や不動産取得税がかかるというデメリットがあります。
改正前民法の遺留分減殺請求権は、現物を取得できる権利だったため、このような問題は生じなかったことを考えると、この点は改正によるデメリットと言えるでしょう。
改正後に発生した相続について、やむを得ず不動産等の現物給付で清算する場合は、遺留分を踏まえた上で、相続人全員で遺産分割協議を行う方が、このような課税の問題を生じずに済むので、お互いにとってメリットがあるかもしれません。
遺言書があっても相続人及び受遺者全員の同意によって遺言と異なる遺産分割協議を行う事は実務上認められています。(ただし受遺者が相続人でない場合は、遺産分割協議によって遺産を取得することはできません。)
円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺留分請求のトラブルを避けるためには専門家に相談しましょう

遺留分請求は法定相続人に認められている権利なので、生前に放棄した場合等を除いて権利行使を止めることはできません。
特定の方に多くの財産を遺すために遺言書を遺すことはできますが、そのことが原因で相続人同士が争う事は望まないという方が多いのではないでしょうか。
自分の死後に家族が遺産を巡ってトラブルにならないようにするためには、遺留分を考慮した上で、遺言書を作成することが重要です。
ただ、遺留分を考えるにあたっては今後のライフプランや生前贈与等も考慮する必要があるので、自己判断は危険です。遺言書を作成する際には、遺産相続トラブル予防に精通した専門家に相談の上、作成することをおすすめします。
遺留分トラブルを避け、円満相続を実現するための遺言書の作成、生前対策に関するご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
※当事務所では遺留分の請求に関する業務は取り扱っておりません。従ってすでに発生した相続について遺留分に関するご質問をいただきましても一切お答えすることはできません。遺留分侵害額請求を検討している方や請求を受けた方は弁護士にご相談ください。
円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

各種サービスの料金はこちら


お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)
0120-546-069